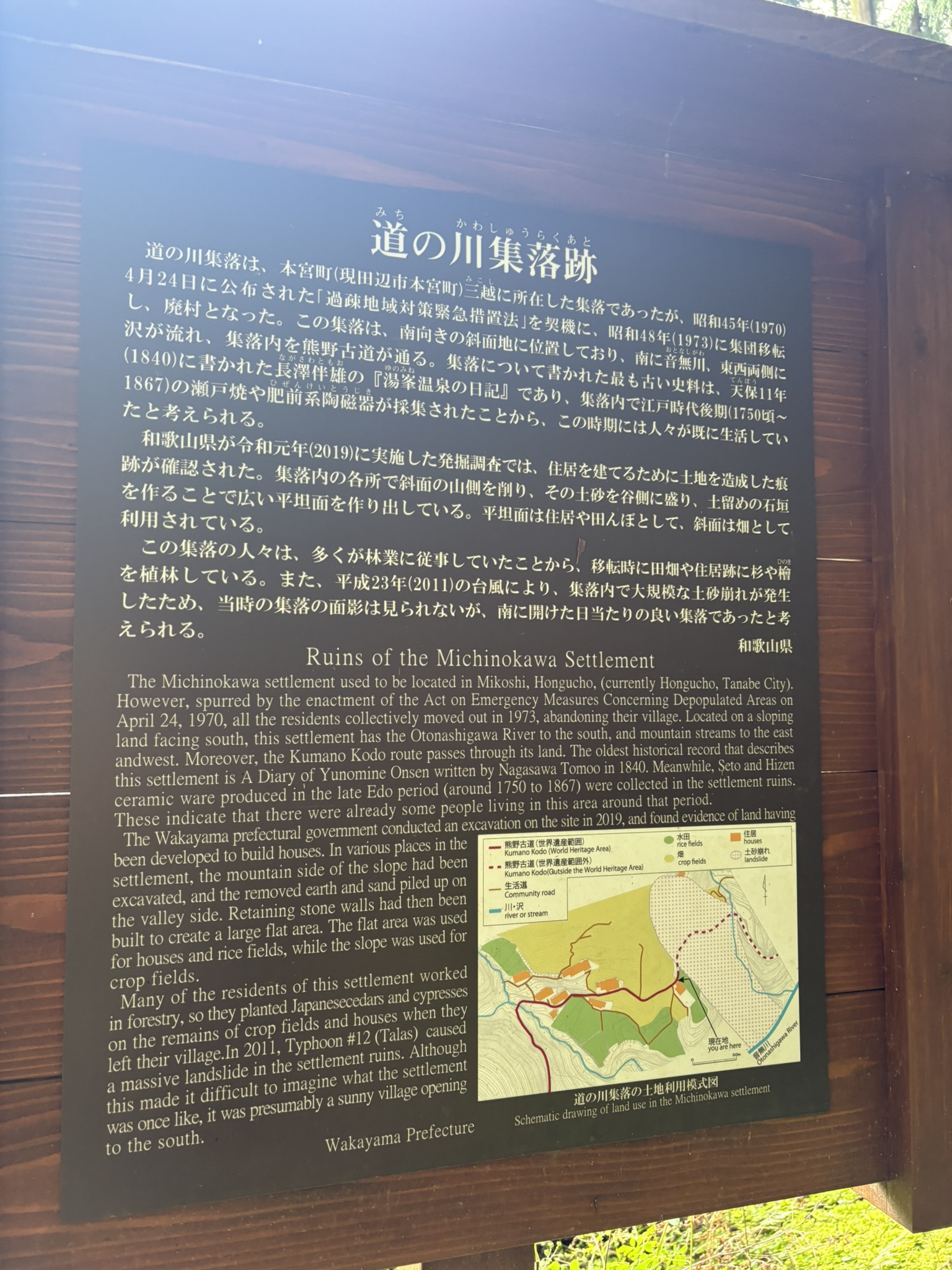






舟玉神社の由来
昔、玉滝という滝があって、その滝つぼで神様が行水をしていると、急に大雨となった。折しも滝つぼに浮かんでいた一匹の蜘蛛がその大雨に溺死しそうになった。それを神様が見て、榊(サカキ)の葉を投げてやった(カシの葉であったという話も)。蜘蛛はその葉に乗って、手足を使って船を漕ぐようにして無事に岸にたどり着いた。その様子を神様が見て、船というものを思い付き、楠をくりぬいて丸木船を造った。これが最初の船であった。
熊野権現の御利益はあらゆる人々に無差別に施されるものだとされましたが、しかし、それも参詣者の日々の精進の上に与えられるものだったのです。道中、所々で祓をし、海辺や川辺では垢離を掻き、身心を清め、王子社では幣を奉り、経供養などを行いました。また、妄語や綺語、悪口、二枚舌など道理に背く言葉は厳禁で、忌詞を用いることにより妄語などを戒めました。
塩垢離や水垢離に湯垢離で身を清め精進することで、熊野権現の御利益にあずかることができる、と考えられていたそうです。
今でも神社では手を清める手水舎ありますけど一緒です。発心門王子まではもうあと少しです。

