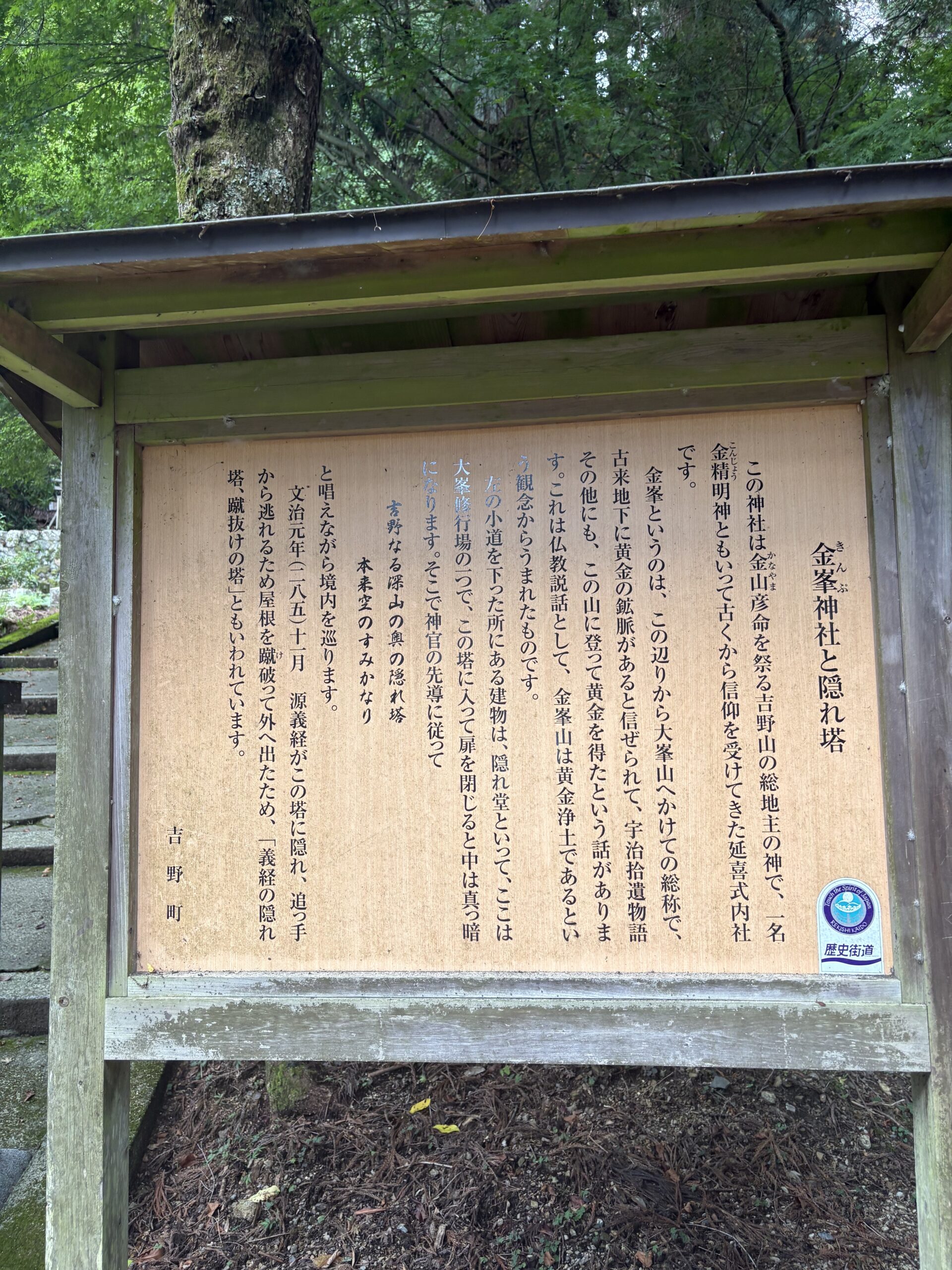金峯神社は、古くから修験道の修行の場であって、神道と仏教が融合した日本独自の信仰が発展しました。
古代における金をはじめとする鉱物に対する信仰を祭祀の起源とする神社で、吉野水分神社とともに「吉野」が信仰の山となる端緒をなしたそうです。
修験道の興隆に伴い峰入の際に行者が通過すべき四つの門が定められたが、金峯山寺銅鳥居を第一の「発心門」とし、第三第四の「等覚門」「妙覚門」が山上ヶ岳に置かれ、当社の社前に第二の「修行門」にあたる鳥居が建てられて、重要な拠点とされました。
修行門(二之鳥居)
金峯神社の北側に位置します。これより先は、民家もなく、空腹と疲労に苛まれながら、四寸岩、小天上、大天井などの山々を越えて、鞍掛け、油こぼし、鐘掛けなどの岩場をよじ登らねばなりません。その苦しい修行の始まりを告げる門といえるでしょう
吉野来てすぐの、発心門は熊野本宮大社にも発心門王子ありますので、ここからは心を高めて発信していきます、という入り口のことです。
ここの金峯神社の修行門(二之鳥居)、金峯神社の北側にあって、これより先は、民家もなく、空腹と疲労に苛まれながら、四寸岩、小天上、大天井などの山々を越えて、鞍掛け、油こぼし、鐘掛けなどの岩場をよじ登らねばなりません。その苦しい修行の始まりを告げる門といえるでしょう。バスはここまでしか来れないですし、吉野の桜や紅葉など楽しむと言ってもまあここの金峯神社まで、ここからは修行の人くらいしか進んでいかないような、そんな場所でもあったりします。